ノートを取ったものの一度も見返さずに忘却の彼方へ消えていく。大体の方がそんな形でノートを取っていることでしょう。
それを解決するノートが「エバーグリーンノート」です。
エバーグリーンノートとよく一緒に語られるZettelkastenとも比較しながら、その真の価値について紹介していきます。
エバーグリーンノートとは?
Andy Matuschakさんが提唱したと言われるEvergreen Note(エバーグリーンノート)。
一言で言えば「進化し、貢献し、何度も蓄積され、プロジェクトを超えて書かれ、整理されるものである。」とAndyさんは語っています。
要は「ノートを取っただけでは終わらない常に進化し続けるノート」ということですね。
このAndyさんが書いたEvegreen notesを参考にエバーグリーンノートについて深ぼっていきます。
ほとんどの人はノートを一時的にしか使えないものにしている
Andyさん曰くほとんどの人はノートをアイデアの受け皿か断片的な考えを書き留めるだけにしか使っていないようです。
このノートの手法は書く分には何も考えなくて済むので楽で良いのですが、こういったノートを何年も書いているとゴミのようなノートの山ができるだけであると語ります。
エバーグリーンノートが知的労働の基本的な単位
進化し続けるエバーグリーンノートであれば、書けば書くほど、溜めれば溜めるほど自分の知識の宝の山ができていくわけです。
もし知的労働者として優れているという指標を一つ定めなければならないとしたら、それは「一日いくつのEvergreen noteを生み出せているか」が私が知る最も良い指標である。
Andy Matuschak
エバーグリーンノートの原則
時間をかけて価値のあるノートを作ることは難しいですが、以下の原則を守ることによってエバーグリーンノートを作成していくことが可能です。
抽象的で理解しづらい内容ですが、なるべくわかりやすく伝えていくよう努力します。
1つの要素で構成されていること
1つのノートは1つのトピックに絞るべきという原則。
ただし、絞りすぎてもいけないという「どっちなんだよ…」とツッコミたくなることも述べています。
まず、ノートの範囲が広すぎる場合は一つのノートと関係する新しいアイデアと出会っても気づかない可能性が多くなったり、そのアイデアをリンクさせる関係性が曖昧になるということが一点。
逆にノートが断片的すぎるとアイデアが繋がっているネットワーク(つまりzettelkastenの本体のようなもの?)も断片的になり、他のノートとのつながりが見えにくくなってしまうということを挙げています。
ちょうど良い感じにノートの内容を絞りましょう(適当)

コンセプト重視であること
著者や本、プロジェクトで整理するのではなく、コンセプトで整理するのがベストであるという原則。
こうすることによってノートを育てていく際に本や著者と言った領域を超えたつながりを発見できると言います。
本や著者などテーマごとにノートを作ることは書く分には簡単だけれども、新しいつながりは、分野を横断したときに発見されます。
コンセプトでノートを整理するとメモを取るのが難しくなりますが、逆にそのアイデアがどのコンセプトに当てはまるのかを考えることにつながるため、ノートを見返すことにつながり、結果的に全く異なる分野のアイデアの間に意外なつながりを見つけやすくなります。
他のノートと密にリンクされていること
1つのノートは他のノートとリンクされているべきであるという原則。
ノートを取っている時に「このノートは何のノートにリンクできるかな」と考えることでそのトピックについてさらに深く考えることに繋がり、古いノートを見返すことにもなるのでノートを見直す動機づけにつながっています。
階層型で整理しないこと
カテゴリーなど決まりきった形で整理しないという原則。
最初から構造があると生まれる可能性のあるアイデアや関連付けを制限してしまうことにつながる。
Andy Matuschak
階層構造が物事を整理する上で自然な構造だと思われていますが、ほとんどの場合、アイデアは異なる階層のアイデア同士で関連することがあります。
アイデアにラベルをつけずに関連付いたアイデアのネットワーク(恐らくZettelkasten本体のこと)を徐々に出現させ、形が見えてくれば新しいカテゴリーが生まれるかもしれません。
エバーグリーンノートとZettelkastenの違い
エバーグリーンノートはニクラス・ルーマンのZettelkastenに大きく影響を受けており、Andyさん自身のアイデアで発展させたものです。
自身のアイデアを自由に加えるために独自の価値観と性向を持つZettelkastenとあえて違う名前を付けることで区別しようとしているようです。
以下で似ている点と異なる点を箇条書きで紹介します。
似ている部分
- 1つの要素で構成されていること
- コンセプト重視であること
- リンクを重視していること
- セレンディピティを美徳とすること(ここよくわからない…)
- 他人のアイデアの要約を蓄積するのではなく、自分のアイデアとその発展を重視すること
- 他人の考えを述べるときでも、自分の言葉を使うことを重視すること
違う部分
| エバーグリーンノート | Zettelkasten |
|---|---|
| ノートを一般的に公開する | ノートを公開しない |
| 創造的なアイデアを生み出す | 主に他人のアイデアについてメモを書く |
| タイトルによる識別 | 数字による識別 |
| 早い段階でノートを作り始める | 関連するノートが溜まってからPermanent Noteを作成する |
Zettelkastenを運用する上でよく使われているObsidianでの日記運用方法についての記事です。
エバーグリーンノートを作る際にも役立つと思うので以下記事もあわせてご参考ください。

エバーグリーンノートについてのまとめ
・エバーグリーンノートは常に進化し、何度も蓄積し、見返され、プロジェクトを超えて書かれ、整理されるもの
・1つのノートは1つのトピックに絞るべき
・著者や本、プロジェクトで整理するのではなく、コンセプトで整理するのがベスト
・1つのノートは他のノートとリンクされているべき
・カテゴリーなど決まりきった形で整理しない
参考文献
noteでも情報発信中
noteではより広く「AI時代の人生戦略」「男磨き」という領域でDoberというブランド名で発信しています。私個人の人生戦略や進捗、Threadsで伸びたコンテンツの深掘りなどを行っているのでぜひチェックいただけると!
最新情報はXやThreadsで発信しているので、そちらもフォローしてもらえると嬉しいです!刻式垢でフォローいただければ発信されている方はフォロバします!仲良くしてください!
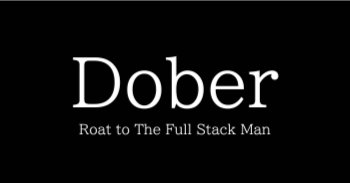








コメント